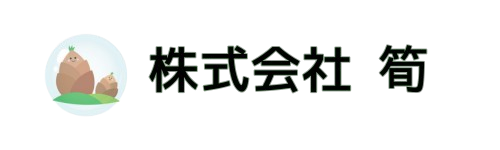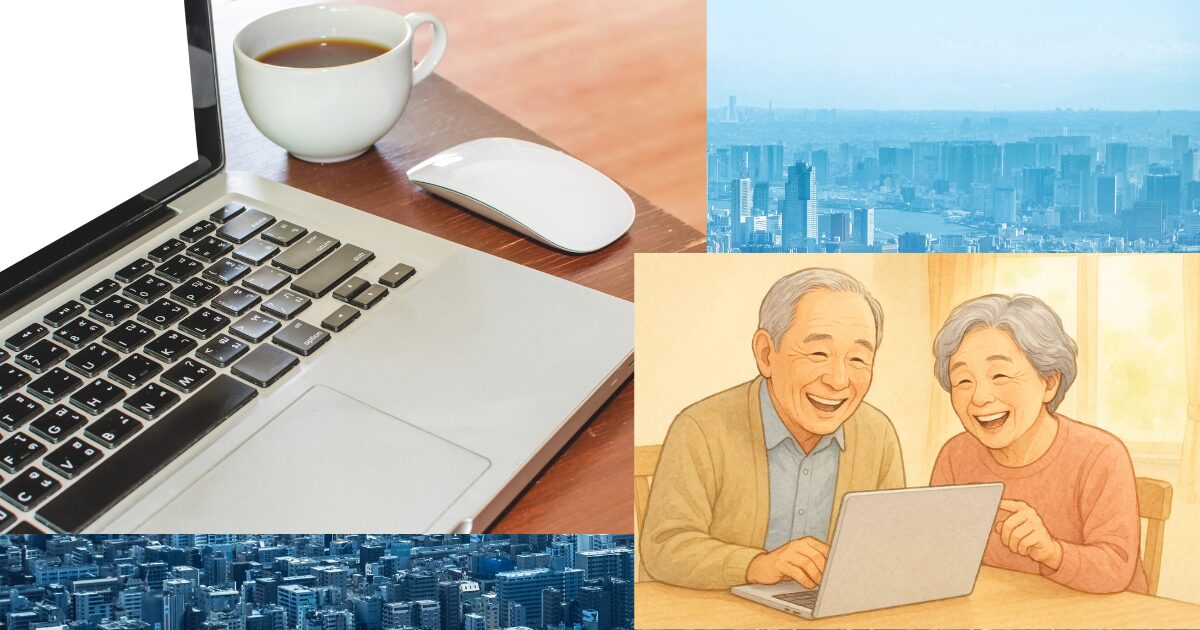2024年度介護報酬改定において、「書面掲示規制の見直し」が決定されました。
全介護サービス事業者に対して、事業所の運営規定などの記載がある「重要事項等」について、これまでの「書面掲示」に追加して、ウェブサイトへの掲載・公表を義務付ける省令/告示/通知の改正が行われました。
これは、インターネット上で情報の閲覧が完結するように、法人の持つホームページなど、または情報公表システムへの掲載が令和7年度(2025年度)から義務化されたものです。
なぜネット上での公表が望ましいとされるのか
少なからず職員も含めて、自社のホームページには誇りを持っているものです。
高い費用や労力を費やし、少しでも事業所の姿勢や方向性を広く知ってもらうために作成している自社のホームページに、行政の指示で「重要事項説明」を掲載するなんて。
と憤慨されている方もおられるようです。
行政は何も、指示や強制をしているわけではありません。ここはひとつ、冷静に内容を読み解き、なぜこの制度が決定されたのかを利用者側に立って認知してみようと思います。
それについてはまず、メリットとデメリット、両方の観点からよく考えてみましょう。
メリット
1.アクセス性の向上と利用者の利便性
利用者や家族は施設を選ぶ際などに、情報を収集するため役所や自治体に問い合わせたり、関係機関から説明書を取り寄せたりする手間がはぶけ、WEB上でいつでも見られて施設比較、事例検討がしやすくなります。
2.透明性の確保
情報を公開することで、運営内容・料金・サービス方針など事業所の実態が見えるようになり、悪質な事業者への抑制効果が見込めます。
3.行政監督・チェックを容易にする
行政が運営指導や監査を行う際に事業所に対し情報公開を義務付けておくことで、公表内容と現状の整合性などが確認しやすくなります。
4.制度のデジタル化・ICT化など効率化の推進
昨今の社会の流れに沿って、福祉分野も例外ではなく、情報提供・保存・公開のデジタル対応をすすめることが求められています。
ホームページなどで公表することで、紙媒体では難しかった更新性や恒常的なアクセスが実現しやすくなります。
5.利用者保護・公平性
地域差や情報格差をなるべく小さくして、誰もが必要な情報にアクセスできるようにする観点からも、ホームページ公開は有効と言えるでしょう。
デメリット
「ホームページで公開」することで事業所のホームページの雰囲気にどう影響するか、またHP離れなどが起こるのではなど、いちばん懸念する所ではないでしょうか
1.デザイン・ブランドイメージとのずれ
公表する「重要事項説明書」などの内容が、量的・文体的に硬いものに成りがちで、事業所のソフトな姿勢や特色を出したい内容と合わない場合が考えられます。
2.情報過多・読みづらさ
利用者や家族がホームページを見た際に、重要事項ばかりが目立って、肝心の事業所が伝えたい案内や雰囲気が伝わりにくくなる可能性があります。
3.更新・管理コスト
情報を正確に最新に保つことが求められるため、更新頻度や責任体制を整備する必要が筆致。そうしないと「古い情報のままで誤解を招く」などのリスクが生じます。
4.ホームページ離れの可能性
情報が硬くてわかりにくい・取っつきにくいなどを一度感じてしまうと、利用者・家族が離れてしまう可能性が考えられます。つまり、ホームページを見に来る機会が減ったり、事業所の印象を悪くしてしまうことが懸念されます。
まとめ(リスクを回避し対処する方法)
制度の両面から検討してみましたが、ともあれすでに決定事項であり、違反した場合は運営基準に違反することになり、行政指導・運営指導の対象になるリスクがありますので、ここは妥協案を構築することといたしましょう。
現状近隣の各事業所を見る限り、自社のホームページに掲載されているところはまだほんのわずかのようです。
そこで、さらによく見ていくと、「情報公表システム」での公表を行っている事業所が増えているようです。
制度上は「WEBサイト(法人ホームページ等または情報公表システム)」への掲載を義務付けており、「自社ホームページでなければならない」と絶対限定しているわけではありません。
それに、全事業所が自社のホームページを持っているわけでもありません。
つまり、「情報公表システム」での公表を認めているのです。
とりあえずは情報公表システムにログインして重要事項をアップロードしておくことをおすすめします。
各自治体のページに情報公表システムへのアップロードの方法が記載されています。
ただし、既述したメリットの観点から行政は、法人のホームページに掲載することを望ましい、と示唆しています。
公表すべき内容としては、「運営規定の概要」「重要事項説明書」「利用料金その他の費用」「営業日・営業時間」「サービス提供地域」「緊急時の対応」「虐待防止措置」など、利用する人が事業所を比較・選定する際の判断材料となる内容となっています。
つまりは、重要事項説明書などと、硬い題目を付けるのではなく、導入しやすい説明書きなど、ホームページの内容に影響しないような工夫ができるのではないかと考えます。
また、上記公表内容をみてすでにお気づきと思いますが、求められているものはまさに情報公表システムに掲載されている内容だということです。
ホームページの雰囲気に影響を与えたくないという事業者は、適切なページから情報公表システムの自社ページにリンクを貼っておくのが良いでしょう。